『老子』:「禅」の源流、全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第四十一章】下士は道を聞かば、大いにこれを笑う。笑わざらば、以て道と為すに足らず。

第四十一章
※書き下し文、現代語訳は、蜂屋 邦夫先生著『老子』 (岩波文庫)を参考にしました。
書き下し文
上士は道を聞かば、勤めて之を行なう。
中士は道を聞かば、存するが若く亡するが若し。
下士は道を聞かば、大いに之を笑う。

笑わざらば、以て道と為すに足らず。
故に建言に之有り。
明道は昧きが若く、
進道は退くが若く、
夷道は纇なるが若し。
上徳は谷の若く、
大白は辱れたるが若く、
広徳は足らざるが若し。
建徳は偸れるが若く、
質真は渝るが若し。
大方は隅無く、
大器は晩成し、
大音は声希かに、
大象は形無し。
道は隠れて名無し。
夫れ唯だ道のみ善く貸して且つ善く成す。
現代語訳(超訳)
優れた士(支配階級に属してその大多数を占め、諸事万端を処理する者)は、道のことを聞くと、力を尽くして実践します。
中くらいの士は、道のことを聞くと、あるときは実践し、あるときは忘れてしまいます。
最も程度の低い士は、道のことを聞くと、大いに笑います。

彼らが笑わないようでは、それは道とするには足らないでしょう。
だから、つぎのような言い伝えがあります。
真に明るい道は、暗いように見えます。
真に進んでいく道は、後退しているように見えます。
真に平坦な道は、でこぼこしているように見えます。
最高の徳は、空虚で低い(水が流れ込む谷)ように見えます。
大いなる純白・潔白は、黒く汚れているように見えます。
広大な徳は、何か足りないように見えます。
剛健な徳を持った人は、怠けているように見えます。
心が質素・純朴で正しい人は、無節操で粗雑に見えます。
大いなる四角形には、角がありません(四角形も無限大にすると円になる)。
大いなる器は、できあがるのが遅いです。(※「大器晩成」として有名な言葉だが、蜂屋先生によれば、大いなる器は、無限の大きさであり、永遠に完成することはない、というのが本来の意味とのこと。完成に向けて永遠に一歩一歩、歩み続ける、ということ。永遠の発展途上。確かにこの方が老子的。完成しちゃったらあとは滅亡、死に向かうだけ。)
大いなる音声は、その音が聞きとれません。
大いなる象には、形がありません。
道は広々と大きく名づけようがありませんが、
そもそも道だけが、万物の生成をよく手助けし、その働きを成しとげさせるのです。
※次章:『老子』全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第四十二章】強梁(きょうりょう)なる者は、其の死を得ず。(DQNは、まともな死に方はしません)

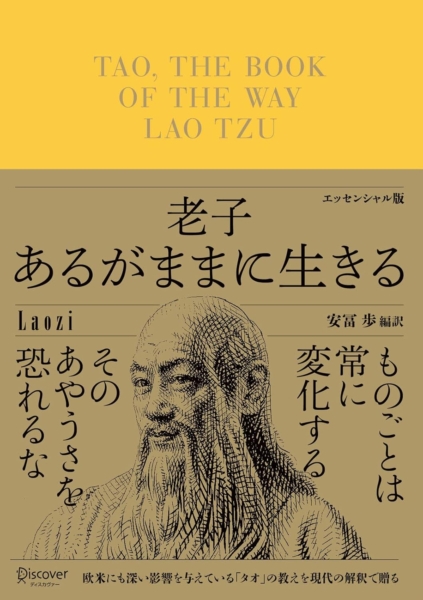
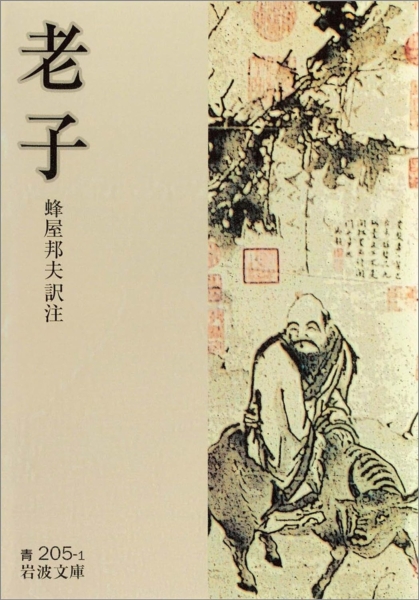
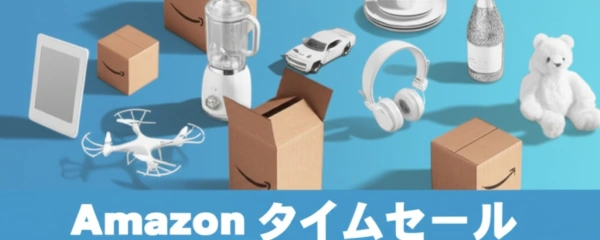




![【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真 【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2025/04/2504141558497456486833490117549611-600x338-1-e1744707846251-150x150.jpg)
車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Sランク🤩】道の駅 こぶちさわ [標高1006m](山梨県北杜市小淵沢町)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/2410232038341425354905474590706832-600x338-1-120x120.jpg)
車中泊は可能?詳細案内図【暫定評価】 【Aランク😄】道の駅 ビーナスライン蓼科湖(たてしなこ) [標高1221m](長野県茅野市)車中泊は可能?詳細案内図【暫定評価】](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2025/05/sss01864-150x150.webp)




車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Aランク😄】木戸池駐車場、キャンプ場🏕️(木戸池温泉ホテル)(車中泊有料) [標高1620m](長野県下高井郡山ノ内町)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/20240924_1543081226103362440604858745-600x338-1-120x120.jpg)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません