『老子』:「禅」の源流、全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第二十二章】自らほこらず、故に功有り。自らほこらず、故に長し。

第二十二章
※書き下し文、現代語訳は、蜂屋 邦夫先生著『老子』 (岩波文庫)を参考にしました。
書き下し文
曲がれば則ち全く、

枉まれば則ち直く、
窪めば則ち盈ち、
弊るれば則ち新たに、
少なければ則ち得、
多ければ則ち惑う。
是を以て聖人は一を抱きて天下の式と為る。
自ら見ず、故に明らかなり。
自ら是とせず、故に彰わる。
自ら伐らず、故に功有り。
自ら矜らず、故に長し。
夫れ唯だ争わず、故に天下能く之と争う莫し。
古の所謂曲がれば則ち全しとは、豈に虚言ならん哉。
誠に全くして之を帰す。
現代語訳(超訳)
曲がりくねった樹木は、曲がっているからこそ柱や梁にされずに天寿を全うできます。

屈まっているからこそ、真っ直ぐになれます(尺取り虫が身をかがめるのは伸びるため)。
窪んでいるからこそ、水が満ちることができます。
衣服が破れているからこそ、新しくできます。
少ないからこそ得られます。
多ければこそ迷い惑います。
そういうわけで聖人は、一なる「道」を抱いて(両極端の対立を平衡させるバランス感覚を持って)、世の中の人々が仰ぎみる模範となります。
自ら見識ありとはせず、自分の物の見方にこだわらない(無我)から、ものごとがよく見えます。
自分が正しいということにこだわらないから、是非が客観的に彰らかになります。
自ら功績を誇らないから、功績が万人に認められます。
自ら才知を誇らないから、いつまでも長つづきします。
そもそも誰とも争わないから、世の中の人々は誰も彼と争うことができません。
いにしえの人が言った「曲がりくねった樹木は、曲がっているからこそ柱や梁にされずに天寿を全うできる」とは、どうしてでたらめなものでしょうか。
まことに、わが身を完全なまま自然に天寿を全うするのです。(※逆に言えば、道に反するもの、俺が俺がと自我にしがみつく者は、自然な死を迎えない、天寿を全うすることはできない、ということ。)
※次章:『老子』全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第二十三章】希言は自然なり

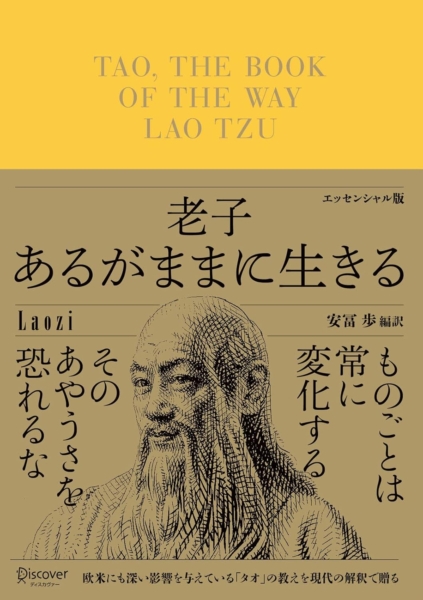
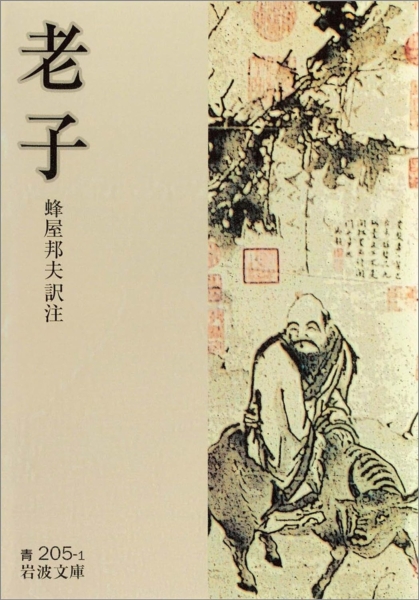
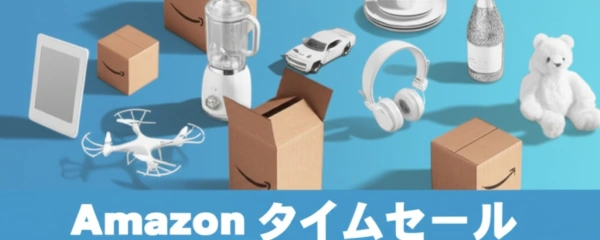




![【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真 【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2025/04/2504141558497456486833490117549611-600x338-1-e1744707846251-150x150.jpg)
車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Sランク🤩】道の駅 こぶちさわ [標高1006m](山梨県北杜市小淵沢町)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/2410232038341425354905474590706832-600x338-1-120x120.jpg)
車中泊適性評価! 【Aランク😄】木戸池温泉ホテル、木戸池駐車場、キャンプ場🏕️(車中泊有料)[標高1620m](長野県下高井郡山ノ内町)車中泊適性評価!](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/20240924_1543081226103362440604858745-600x338-1-120x120.jpg)
トイレのスペックは?車中泊は可能? 【良😊】道の駅 美ヶ原高原🏔️ [標高1970m](長野県上田市)トイレのスペックは?車中泊は可能?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/09/20240926_1332268688553999409551432096-600x338-1-120x120.jpg)

車中泊は可能?トイレは利用可能? 【良😊】高峰マウンテンパーク【静寂😴】 [標高1924m](長野県小諸市)車中泊は可能?トイレは利用可能?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/09/20240924_2112123367851507519315388-600x338-1-120x120.jpg)
車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Sランク🤩】道の駅 なるさわ [標高990m](山梨県南都留郡鳴沢村)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/2410241458135525494321063371435186-768x432-1-120x120.jpg)
![【Aランク😄】高峰高原ビジターセンター [標高1964m] (群馬県吾妻郡嬬恋村)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Aランク😄】高峰高原ビジターセンター [標高1964m] (群馬県吾妻郡嬬恋村)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/20240925_0933224974698694502812585151-600x338-1-120x120.jpg)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません