『老子』:「禅」の源流、全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第二十五章】道は自然にのっとる

第二十五章
※書き下し文、現代語訳は、蜂屋 邦夫先生著『老子』 (岩波文庫)を参考にしました。
書き下し文
物有り混成し、天地に先だちて生ず。

寂たり寥たり、独立して改まらず、周行して殆まず。
以て天下の母と為す可し。
吾れ、其の名を知らず、之に字して道と曰い、強いて之が名を為して大と曰う。
大なれば曰に逝き、
逝けば曰に遠く、
遠ければ曰に反る。
道は大なり、天は大なり、地は大なり、王も亦た大なり。
域中に四大有り、而して王は其の一に居る。
人は地に法り、
地は天に法り、
天は道に法り、
道は自然に法る。
現代語訳(超訳)
「何か」が混沌として運動しながら、天地よりも先に誕生しました(ビッグバン)。

それ(道)は、ひっそりとして形もなく、ひとり立ちしていて他の何物にも依存せず、あまねくめぐりわたって休むことがありません。
この世界の母ともいうべきものです。
わたしは、その名を知りません。
仮の字(実体を表す「名」に対して、世の中に通行させる呼び方)をつけて「道」と呼び、あえて無理に名をつけるとして「大」(大いなるもの、無限なるもの)と言いましょう。
大いなるものはどこまでも動いてゆき、
どこまでも動いてゆくと遠くなり、
遠くなるとまた根源に返ってきます。
「道」は大なるもの、「天」は大なるもの、「地」は大なるもの、そして「王」もまた大なるものです。
この世界には四つの大なるものがあり、王はその一つを占めています。
人は地のあり方を手本とし(土地の実勢に合わせて農業をしたり生活する)、
地は天のあり方を手本とし(大地の植物は天から降る日光や雨によって生育する)、
天は道のあり方を手本とし(天の秩序は宇宙エネルギーとも言うべき「道」に従う)、
道は自ずから然るあり方(あるがままであること)を手本とします(水が四角の器に入れれば四角に、丸い器に入れれば丸くなるように、あるがまま)。
※次章:『老子』全文 書き下し文と現代語訳(超訳)【第二十六章】重きは軽きの根たり、静かなるは躁がしきの君たり

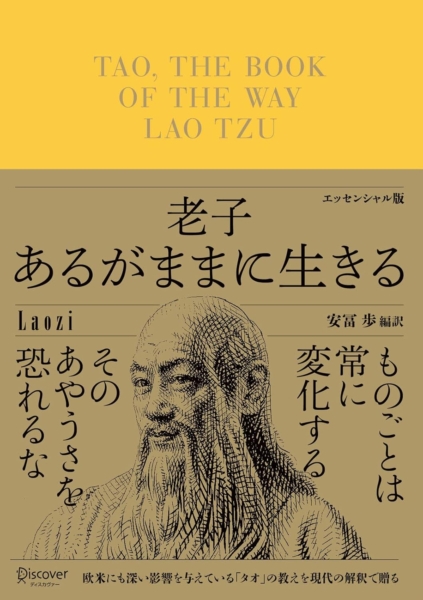
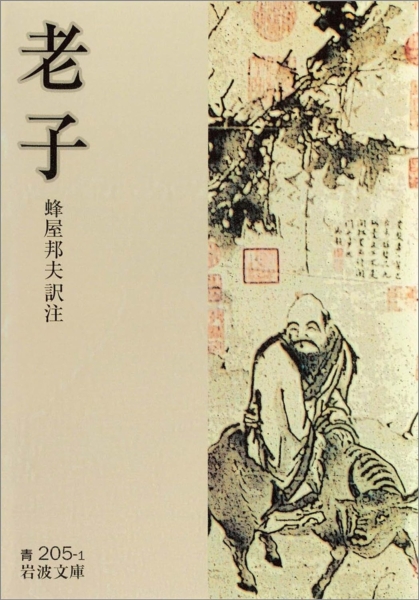
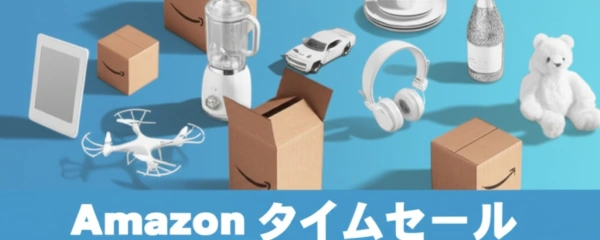



車中泊適性評価! 【Aランク😄】木戸池温泉ホテル、木戸池駐車場、キャンプ場🏕️(車中泊有料)[標高1620m](長野県下高井郡山ノ内町)車中泊適性評価!](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/07/20240924_1543081226103362440604858745-600x338-1-120x120.jpg)

![【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真 【Sランク🤩】木曽駒冷水公園【究極の無料キャンプ場🏕️】、木曽駒ヶ岳 コガラ登山口駐車場 [標高1290m]「上善は水のごとし」(長野県木曽郡木曽町)車中泊は可能?詳細案内図とトイレ写真](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2025/04/2504141558497456486833490117549611-600x338-1-e1744707846251-150x150.jpg)
トイレのスペックは?車中泊は可能? 【良😊】道の駅 美ヶ原高原🏔️ [標高1970m](長野県上田市)トイレのスペックは?車中泊は可能?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/09/20240926_1332268688553999409551432096-600x338-1-120x120.jpg)
車中泊適性評価!⇨採点結果は何点? 【Sランク🤩】須川駐車場、須川野営場(無料キャンプ場)、須川ビジターセンター駐車場 [標高1118m](岩手県一関市)車中泊適性評価!⇨採点結果は何点?](https://syachuhaku-blog.fxtec.info/wp-content/uploads/2024/09/20240916_1744479806394113907937778872-120x120.jpg)




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません